お風呂
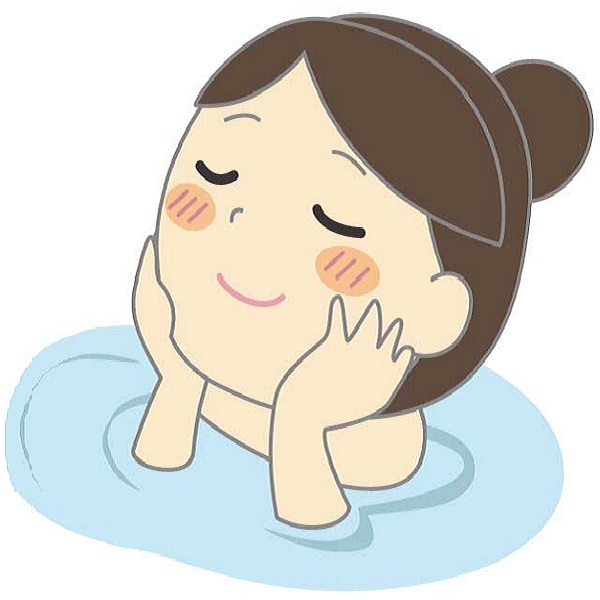
精油をお湯に入れて香りを楽しみながら入浴する
「沐浴法」(アロマバス)は
入浴の温熱効果と精油の相乗効果でアロマを楽しむ方法です。
アロマバスの効用
温浴することで血行が良くなり、
揮発した精油成分を含む水蒸気を吸い込むことで、呼吸器から、
そして皮膚からも精油成分を取り入れることが出来ます。
また、アロマバスに浸かることで、
活動モードになっていた自律神経をリラックスモードに変え、
心地よく眠るのにも役立ちます。
お湯を入れた洗面器に精油を垂らし、お風呂の蓋に置くだけでもOK!
湯船に精油を直接入れないので、家族に気を使うことなく、
ゆったりと香りを楽しめます。
全身浴法
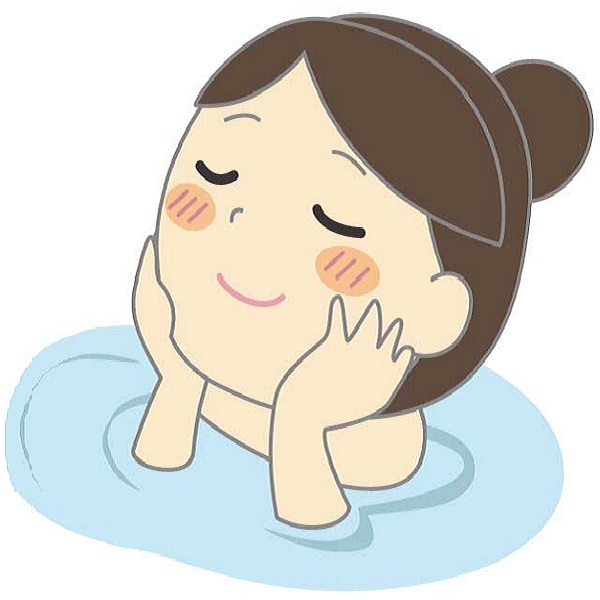
湯を張った浴槽に用途に応じた精油を入れ、肩までつかります。
疲労回復やリラックスさせたい時には、
ぬるめの湯(38~40℃程度)でゆっくりリフレッシュしたい時は、
少し熱めの湯(40~42℃)にして短時間で、
眠気を取り、元気になりたい時には、42℃以上の温度にします。
[精油分量]1~5滴 

半身浴法
湯を張った浴槽に精油を入れ、みぞおちまで浸かる方法です。
湯はぬるめにして、20~30分位ゆっくり時間をかけて浸かります。
全身浴法に比べ、心臓や肺への負担が軽く、のぼせにくいので、
ゆっくり長時間体を温めるのに適しています。
冷え性、むくみ、デトックス、府民の解消など、様々な効果が期待出来ます。
上半身を冷やさないように、タオルをかけるなど工夫しましょう。
[精油分量]1~3滴 

足浴(フットバス)

足浴は深めの洗面器やタライ、バケツなどに、
少し熱めの湯を両足のくるぶしが浸かる程度に張り、
無水エタノールに混ぜた精油を入れ、5~20分足を浸ける方法です。
足を温めることで、全身の血行が良くなるので、
冷え性や足のむくみにおススメです。
手浴(ハンドバス)
器に張ったぬるめの湯に無水エタノールに混ぜた精油を入れ、
5~10分程、手首まで浸す方法です。
腕から肩にかけても温まるので、
冷え性の他、肩こり、頭痛、手荒れの緩和にもなります。
両肘を湯に浸す、「肘浴」もおススメです。
クラフト
バスオイル
精油は脂溶性なので、オイルで希釈すると刺激が少なくなります。
塩を使うバスソルトとは異なり、バスオイルは保湿効果に優れます。
お湯の中に入れてかき混ぜ、入浴しながらゆっくりと深呼吸しましょう。
アロマバスソルト

精油を塩に混ぜることで、精油がお湯に拡散しやすくなります。
天然塩はミネラルも豊富で、発汗作用もあり、美容にも効果的です。
アロマバス重曹
重曹を用いると、肌あたりが柔らかい入浴剤になります。
重曹は「炭酸水素ナトリウム」とも呼ばれ、
弱アルカリ性の性質を持つ粉末です。
血行を促進する効果が期待出来ます。
保温効果があると言われているので、お風呂上がりもポカポカ、
冷えに悩んでいる人には、重曹を使った入浴剤はピッタリです。
更に重曹には、
皮脂や角質を落とす効果や消臭効果も期待出来るので、
体臭が気になる人にもオススメです。
アロマバスミルク
ミルクの保湿効果で肌がしっとりとします。
但し腐りやすいので、入浴後はすぐに水で洗い流して下さい。
アロマバスハニー
ハチミツには肌に潤いを与える「保湿効果」があります。
その他、殺菌作用や炎症を抑える作用など、
スキンケアに欠かせない幅広い美容効果があるとされています。
世界三大美女の一人のクレオパトラも
美容のためにお肌にハチミツを塗っていたという伝説もあるほどです。
バスフィズ・バスボム
バスタブに入れるとシュワーっと溶けるバスフィズ。
可愛らしいものが市販でも沢山売られています。
使用する材料によって、様々な効果もプラスすることが出来ます。
<レシピ>
注意
|





